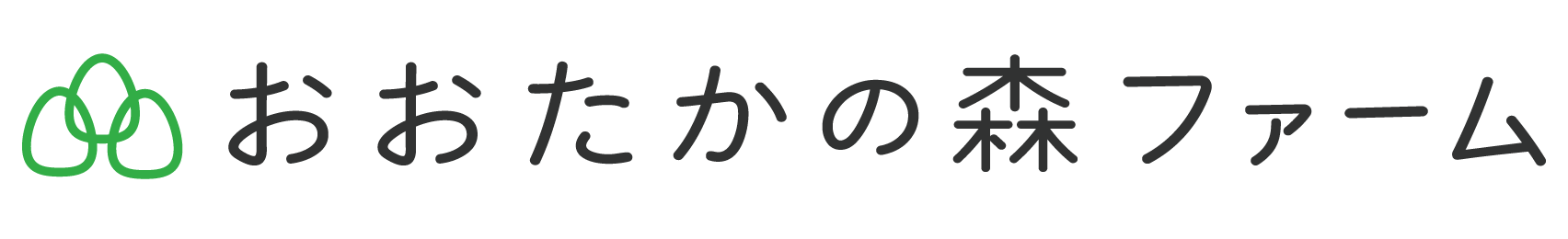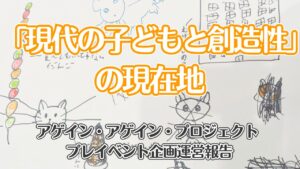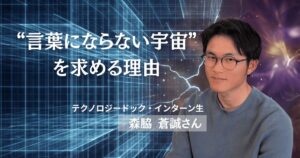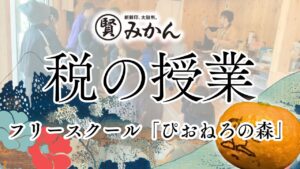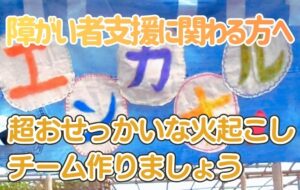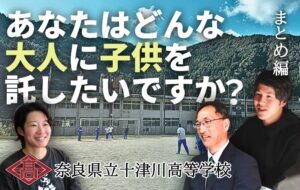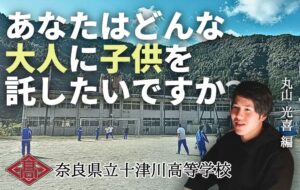うちの息子は中学1年生。
勉強が好きかと聞かれたら、迷いなく「NO」だろう。
好き嫌いと得意不得意はまた別問題だが、少なくとも親の私から見て「勉強が得意そうだ」と感じたことはない。
だからこそ、私は「勉強をしろ」とは言わないようにしている。

その代わり、彼には明確な“好き”がある。
それは「誰かの役に立つこと」だ。
イベント運営などで手伝いをお願いすると、率先して動いてくれる。
「働くこと」への前向きさや素直さが彼の大きな特性であり、
彼自身も「勉強するくらいなら、早く働きたい」と公言している。
ただ、その言葉に私は少し引っかかっていた。
「勉強が嫌だから労働に逃げたい」のか?
それとも「社会の中で、自分の学びを自分で見つけていきたい」のか?
親としては、その境界線が気になっていた。
そんな息子が見せた、“ある奇跡”の話をしたい。
火起こし名人さえもあきらめた日
それは、とある自然体験の場でのことだった。
酷暑と高湿度で、予定していた火起こしのプログラムは断念されることになった。
火起こしの名人ですら「今日はつかない」と判断するほどのコンディション。

予定されていた工程は飛ばされ、子どもたちは串刺しの鮎を焼く作業へと移っていった。
誰もが火起こしのことなど忘れかけていたそのとき、
うちの息子だけが、黙々と火起こしの器具を握り続けていた。
しかも彼が手にしていたのは、軸がぶれていて回しにくい不良品。
火が起きる気配などまったくない。

しかし息子は手を止めなかった。
誰に言われるでもなく、誰に見られるでもなく。
私は、彼が一点集中すると時間を忘れる性格だと知っていたので、ただ黙って見守った。
やがて火起こし名人が席を離れた瞬間を見計らって、
息子はこっそりと“精度の高い器具”へ持ち替えた。
そしてまた、キュッキュッと音を立てながら回し続けた。

その傍らにずっといてくれたのが、三角さんだった。
彼は息子のバディとして、一緒に火起こしに挑み、手を添え、励まし続けてくれた。
後に三角さんはこう語ってくれた。
「頑張ってる姿に、応援したくなったんです」と。

「誰も見ていない場所」で起きたこと
火起こしの時間はとっくに終わり、
誰も注目していない片隅で、息子と三角さんは火を追い続けた。
串刺しの鮎が焼かれ、笑い声があがる横で、
ただ黙って、ただただ火の“あいつ”を生み出すために手を動かしていた。
そう、火起こしにおける“あいつ”とは、
摩擦で生まれる黒く小さな火の種のことだ。
それを見逃さず、麻に包んで酸素を送り、発火に導く。
技術も体力も必要な作業。成功確率は、プロでも五分五分だ。
そして、ついにその瞬間が来た。
煙の中から、“あいつ”が現れた。

火起こし名人が気づき、すぐに麻を用意し、
酸素を送り込み、回す。

「ついた!」
まさかの発火。
しかも、あの名人でさえ諦めた条件で。
それを、誰にも見られていない場所で、
誰からも命じられていない子どもが成し遂げた。
人々が集まり、火を囲み、驚きと称賛の声が広がった。
「すごい!」「やったね!」「信じられない!」
その場の空気が一変した。
火を起こしたのは、誰のためでもなかった
後で息子に聞いた。
「何であんなに頑張ったの?」
彼はこう言った。
「火を起こしたかっただけ。“あいつ”を見つけたかった」と。
褒められたいわけでもない。
誰かに勝ちたいわけでもない。
ただ、「火を起こしたい」という純粋な衝動。
そして、最後まで隣にいてくれた三角さんの存在。

自分の中の「火」を起こす
私はこの出来事に、ひとつの答えを見た気がした。
息子は勉強が嫌いだ。
だが、彼には自分の火を起こす力がある。
誰も見ていないときに、誰のためでもなく、自分の衝動に従って努力できる力がある。
それは、数字の成績や偏差値では測れない。
だけど社会に出たとき、何より大切な力ではないだろうか。
私は、これを「奇跡」だとは思わない。
むしろ息子の中に元からあったものが、
自然と人と時間の中で、ようやく火がついたのだ。

この体験をくれた場と人に、心から感謝したい。
そして彼の中の火が、これからどんな風に燃えていくのか——
親として、静かに見守っていきたいと思っている。