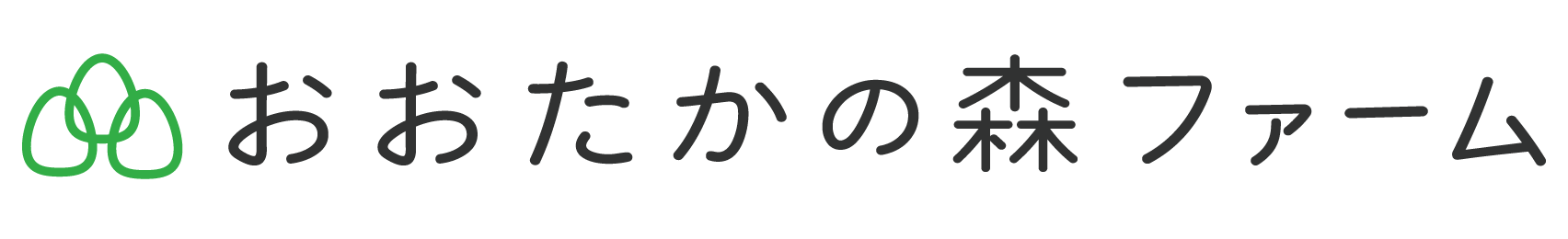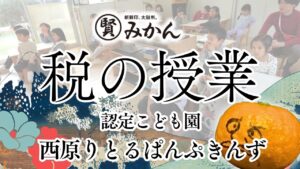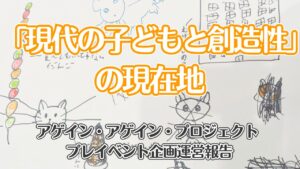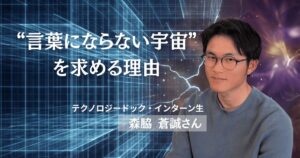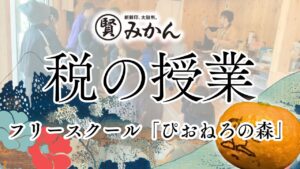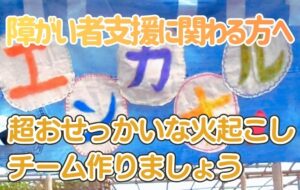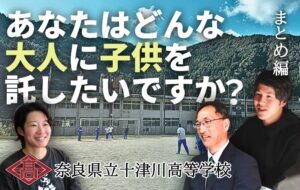先日、千葉県倫理法人会のモーニングセミナーにて、「ナラティブとセオリーの衝突」というテーマで講話をさせていただいたときのお話です。

今回の登壇は、岡本会長のご厚意によるものだった。
正直、私は朝がとても苦手だ。
当日は朝5時集合。まだ夜のような暗さの中でリハーサルを行い、
声を張り上げての朝礼から一日が始まった。
20年前にも一度、同じ会に参加したことがあるが、
そのときは「強制的にやらされている」という印象しか残らず、入会には至らなかった。
それが今回は、まったく違う感覚を得た。
3歳で気づいた “ 儀式 ” の意味
年齢を重ねると、日々の中に緊張感や通過儀礼のような瞬間が少なくなっていく。
理不尽なことや不条理はあっても、それを通じて心が引き締まる機会は減っていく。
そんな中で、早朝にお腹から声を出し、姿勢を正し、「はい」と返事をする
一見単純な行為の中に、忘れていた感覚があった。
それはまさに “ 初心に帰る ”という体験だった。
さらに、この場を支えているのは、地域の経営者や会長、社長といった方々。
世代を超えて同じ所作を行い、朝の空気を共有するということ自体に、
ある種の清らかな緊張感があった。
倫理法人会という場が、単なる経営団体ではなく、
「非日常の儀式としての学びの場」であることに、初めて気づかされた。
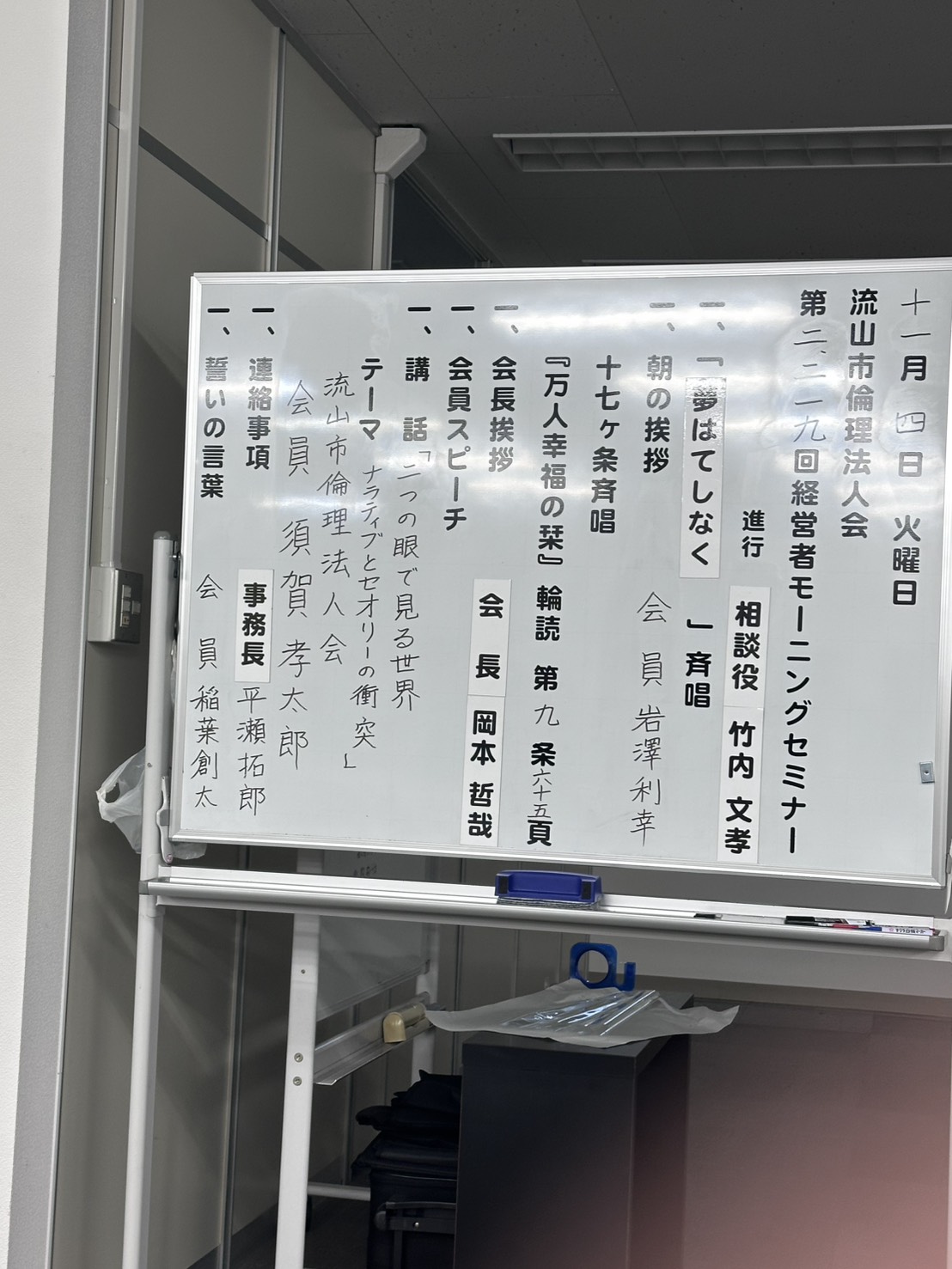
自分を“開く”体験としての講話
私はこれまで、人前で話す機会には比較的慣れている方だ。
しかし今回は、地元で育ち、子供の頃から知っている人たちの前、
しかも実績ある経営者たちを前にして話すという、
まったく異なる種類の緊張感があった。
内容そのものよりも、「自分がどのように受け止められるか」を超えて、
純粋に“今この瞬間を乗り切る”という感覚に集中していた。
それは、プレゼンでも講演でもない、
“心の筋肉を試される場”のようでもあった。
終えた後には、久しぶりに「やりきった」という達成感が残った。

倫理法人会という「非日常の学校」
この体験を通じて、私は改めて感じた。
倫理法人会は、商工会やビジネス交流会とは本質が異なる。
それは、経営のノウハウを学ぶ場ではなく、
「経営者が人間としての原点を思い出す場」なのだ。
言葉を変えれば、
“ 形式を通して心を整える ” ことに価値がある場所。
若いころはそれが形式的に見えたが、
今はその「型」の中にこそ自由があると感じる。
結び
全国に広がるこの会にせっかく入ったのだから、
どれだけ自分の中の解像度を高められるかを、これからの挑戦としたい。
倫理法人会は見学無料で、誰でも参加できる。
朝が得意な人はもちろん、むしろ朝が苦手な人にこそ、
この“非日常の朝”を体験してほしいと思う。
最近は若い世代の会員も増えているそうだ。
私自身も、43歳にして再び「朝の意味」を学び直した。
それは、単なる早起きではなく、
“心の姿勢を整える時間”だったのだと今は思う。