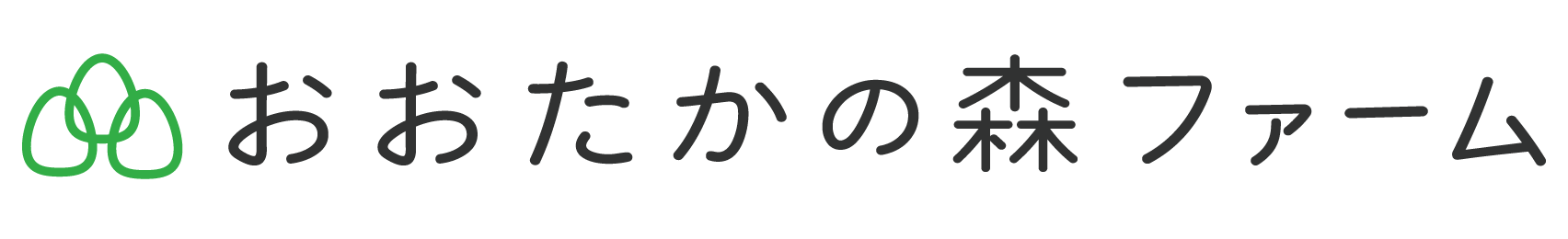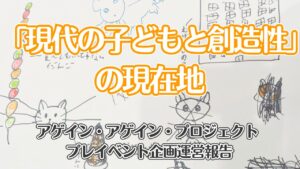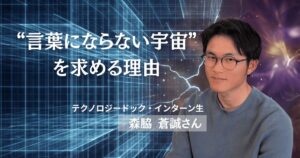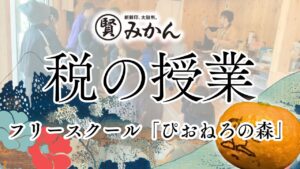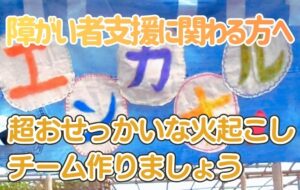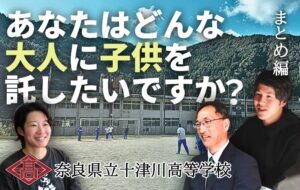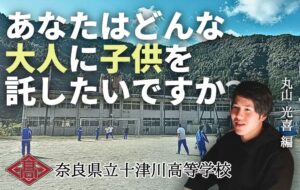私がアザドさんと向き合ったとき、最初に感じたのは不思議な安心感だった。日本に帰化して暮らすバングラデシュ出身の彼は、熱心なイスラム教徒であり、誠実そのものの人柄を漂わせている。国籍や文化の違いを超えて、同じ 「教育」というテーマを語り合える相手がいることに、私は心から嬉しさを覚えた。

ふるいにかける教育から、学び合う教育へ
日本の教育は、長らく「ふるい」にかける仕組みだった。優秀な豆だけを残し、小さな豆は振るい落とされる。その結果、落とされた豆たちの持つ独自の旨みは失われてしまう。
私は教育とは本来、その小さな豆を含めて編成し直すことだと考えている。
この仮説を話すと、アザドさんは深く頷いた。彼はこう言いました。
「人はそれぞれ価値がある。国籍や宗教に関わらず、価値は必ず存在する。そしてその価値は、挨拶や約束を守るといった小さな行動に現れる」
その言葉に、私は自分の考えが世界とつながった瞬間を感じた。
信仰が与える冷静な視点
イスラム教徒であるアザドさんの話には、信仰に基づいた冷静さがあった。男女の役割について問うと、彼はこう語った。
「女性が家庭を守るという考え方は、上下の話ではなく、歴史的に安全や共同体を守るための合理的な設計だったのです」
現代社会では「男女平等」が強調されすぎて、ときに新しい同調圧力を生んでいる。アザドさんの視点は、その矛盾を切り取る。役割は差であって、上下ではない。その差異をどう設計するかが大切なのだ。私はその言葉に、教育や社会の制度設計にも通じる普遍性を見た。

都市と地方、同じ国の中の多様性
印象的だったのは、アザドさんが語ったマレーシアの例だ。
首都クアラルンプールでは女性が社会で大いに活躍しているが、少し離れた地方に行くと伝統的な役割が色濃く残っている。一つの国の中に多様性が共存しているという事実は、私の仮説を裏づけるように響いた。価値観は絶対化するものではなく、相対化して見つめ直すものだ。

信用は小さな行動から
アザドさんが繰り返し強調したのは「信用」の力だった。都市部では人々が互いに無関心になりがちだが、地方や小さな共同体では挨拶やお裾分けといった日常のふるまいが、信用を積み上げていく通貨になる。信用は制度やKPIでは測れない。だが、小さな行動の積み重ねとして可視化できるものだという考えは、私の「学び合い」というテーマと深く響き合った。

対話から得た確信
この日の対話で、私は確信した。
差異は分断の原因ではなく、学び合いの資源になる。役割は固定ではなく、設計の問題である。
そして信用は、小さなふるまいの積み重ねで生まれる。アザドさんの誠実な姿勢と静かな語り口は、その確信を強く支えてくれた。
終わりに
教育も社会も、正しさを競うのではなく、人の価値をどう配置するかが鍵になる。
制度の外側にある日常のふるまいから、学び合いは始まる。
アザドさんとの対話は、その第一歩をどう踏み出すかを教えてくれたのだ。
そして彼は、ビジネスにおいてもその哲学を実践している。日本で自動車関連事業を展開し、誠実さと信用を軸に顧客の信頼を積み重ねている。詳しくは公式サイトをご覧いただきたい。
Freedom Online(https://freedomonline.jp/)