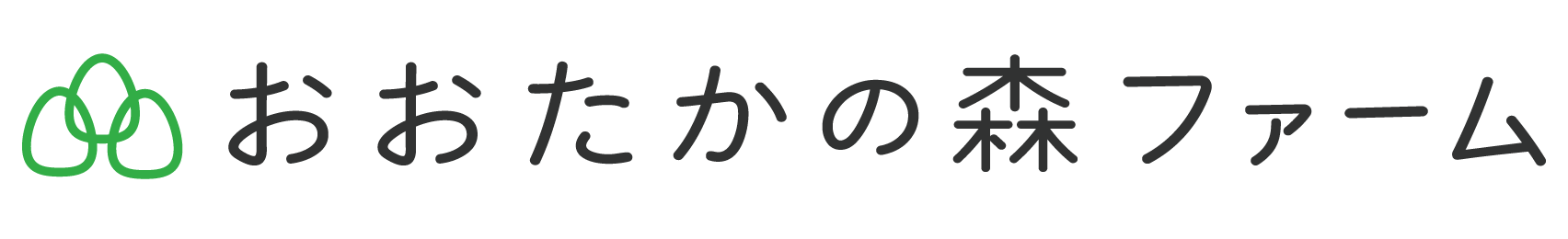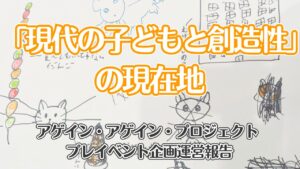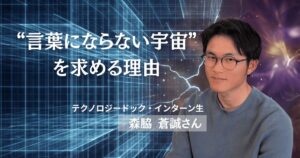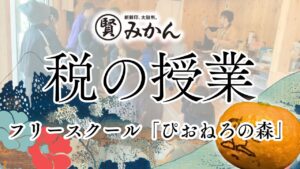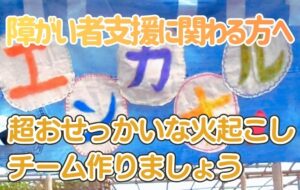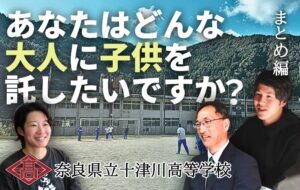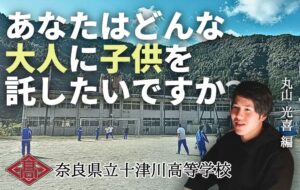「陸上競技を、もう一度人間の手に取り戻す」
原山享大氏は、一般社団法人ビーチ陸上競技連盟 代表理事で世界陸上の公式計測も手がける、陸上界では知られた技術者だ。
そんな“ゴリゴリのエンジニア”である彼が、今あえて「ビーチ陸上」という新しい競技を提唱している。

きっかけは単純な疑問だった。
“ビーチバレーやビーチサッカーはあるのに、なぜビーチ陸上はないのか?”
だがその背後には、長年陸上競技を見つめてきた人間だからこそ抱く、深い違和感がある。
それは、陸上競技が “ 崇高すぎる存在 ” になってしまったことへの寂しさだ。
記録が更新されるたびに湧き上がる歓声の裏で、一般の人が「走る」という行為から遠ざかっていく。
そんな現状に、原山氏は静かに警鐘を鳴らしている。
道具と記録の先にある「公平さ」
厚底シューズ、高速トラック。
記録を伸ばす技術の進化は、スポーツ界の誇りでもある。
しかし原山氏は問う。
「道具の差が記録の差になる競技は、公平といえるのか?」
彼が提唱する「ビーチ陸上」は、すべてを裸足で行う。
そこにあるのは、古代オリンピックのように人間本来の身体性だけを競う純粋な世界だ。
「誰もが同じ条件で挑める競技をもう一度」 という願いが、砂浜の上に新しい陸上文化を生みつつある。

走って気づいた「泳ぐような走り」
実際に私自身も、原山氏のイベントでビーチを走ってみた。
砂浜を50メートル、タイムを意識して本気で走る。
それは「走る」というよりも、水をかくように身体全体で前へ進む感覚だった。
力を入れすぎると進まない。
押すでもなく、弾くでもなく、“抗う”ように進む不思議な動き。
そこには、スピードやテクニックではなく、身体の使い方そのものが問われる面白さがある。
普段、私たちは裸足で全力で走ることなどほとんどない。
だからこそ、この競技は単なる運動ではなく、非日常の感覚を呼び覚ます体験だった。

「つまずかない身体」と「舗装された社会」
もう一つ印象的だったのは、誰も転ばなかったことだ。
砂浜にはコースを区切る紐や電線が引かれていたのに、子どもも大人もつまずくことなく走り抜けていった。
それはつまり、誰も足を引きずっていなかったということ。
現代の舗装された道を歩くとき、私たちは無意識のうちに“滑るように歩いている”。
しかし砂浜では、しっかり足を上げないと前に進めない。
昔の人はこうして歩いていたのだろう。
そう思うと、便利さの代償として、私たちは身体の「生きる力」を失いつつあるようにも感じた。
歩くこと、走ること。
それは本来、命とつながる行為だったはずだ。

ビーチ陸上が投げかける問い
この競技の魅力は、「速さ」や「勝敗」を超えたところにある。
スポーツと健康、スポーツと人生、そしてスポーツと哲学。
それぞれの人が、自分なりの“走る理由”を見つけることができる。
表現しづらい理念だからこそ、誤解されやすい。
しかし、そこに関わる人々の共感の強さは本物だった。
陸上競技を、もう一度 “ 人間の手 ” に取り戻す。
その挑戦は、ただの新競技の誕生ではなく、身体と社会の再接続なのかもしれない。

【結び】
砂の上を裸足で走るとき、人は誰よりも「人間」に戻る。
道具に頼らず、地面の感触を足で感じながら進むその瞬間、
記録や順位を超えた“原点のスポーツ”が立ち上がる。
それが、ビーチ陸上の本当の魅力だ。