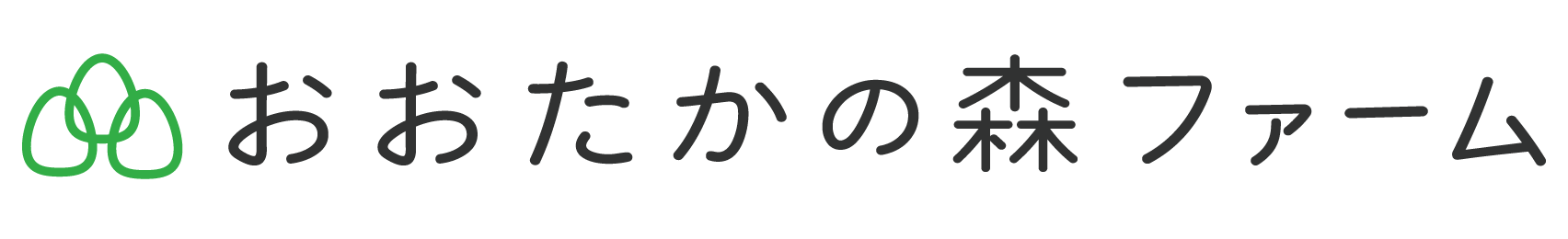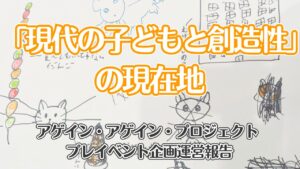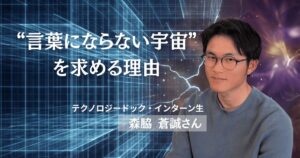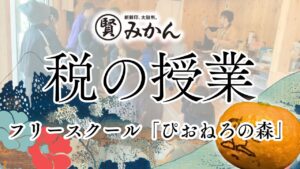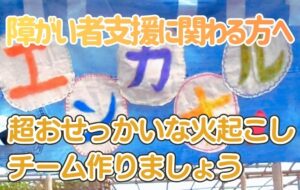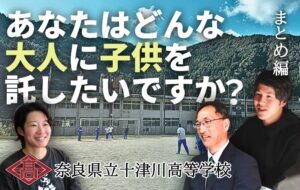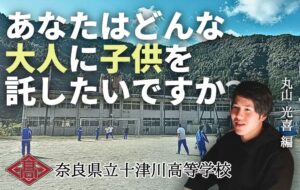私が株式会社ストラートデザイン代表 大德弘恵(だいとく ひろえ)さんと出会ったのは、ABEMAPrimeの番組での共演がきっかけだった。
当初の企画は「片付ける派の大德さん」対「散らかす派の私」という、まるで正反対の立場をぶつけ合う“バーサス構造”だった。

けれど、実際に対話を重ねるうちに見えてきたのは、私たちの方向は決して逆ではなかったということだ。
「整える」か「散らかすか」という表層的な対比の奥に、共通して流れていたのは“思考を整理する”という同じ目的地。
空間を整えるか、概念を解きほぐすか違うのは手段であって、本質は同じ構造にあった。
この気づきがきっかけで、後日私はストラートデザインのオフィスを訪ね、大德さんの歩んできた道と、今の事業の核心にある思想を聞かせてもらった。
その時間は、単なるインタビューではなく、女性経営者という存在が社会の中でどう成熟していくかを体現する一つのケーススタディのようだった。
「こんなビジネスがあったらいい」から始まる現実的な創造力
大德さんが最初に手がけたのは“片付け”の世界だった。
しかし、単なる整理整頓ではなく、彼女の視点には初めから「構造を見る目」があった。
設計者がレイアウトを描き終えた後に、最後に残ったスペースを「収納」にあてる
そんな業界慣習に違和感を覚えたという。
紙を七割削減しないと入らない、五割減らさないと収まらない
そんな“根拠なき削減率”を設計者が苦しげに口にする姿を見て、
「私がその“根拠”を作れるかもしれない」と気づいた瞬間、彼女のビジネスは動き出した。
つまり、感覚的に扱われてきた“片付け”という領域を、
データとプロセスで語る 「収納コンサルティング」という新しい業種に変換したのである。

「感覚」を「データ」に変える力
大德さんの言葉で印象的だったのは、「収納をロジックで語る」という一言だ。
オフィスの美しさや快適さは、感覚的な言葉で語られることが多い。
だが、経営判断を担う多くの男性経営者にとって、それは“納得の根拠”になりにくい。
そこで彼女は、収納量・使用頻度・動線などをすべて定量化し、
「このデータに基づいてこのルールを作ります」と提示する仕組みをつくった。
感覚を構造に置き換え、感性を数値で支える。
このアプローチは、単に説明しやすくするためではない。
それは「感性とロジックの間に橋を架ける行為」であり、
つまりは“女性的感性を社会に翻訳する”知的営みでもある。
こうして彼女の会社は、オフィス業界で唯一無二の収納コンサルティング企業へと成長していった。
柔軟な経営こそ、真の知性である
男性経営者が理念や夢を掲げる強さを持つ一方で、
プライドが変化を阻むことも少なくない。
しかし大德さんは、現実を観察し、変化を戦略に変える柔軟さを持っていた。
単体では予算が取れない収納コンサルティングを、
「オフィス移転プロジェクト」や「レイアウト変更プロジェクト」の中に組み込み、
“一体化戦略”として展開する。
つまり、 「お客様の課題を解くために自分の形を変える」という発想である。
この柔軟さは、単なる適応ではなく、構造を変える知性だ。
女性経営者が持つ「共感の力」を、戦略的な構造変換へと昇華させた姿に、
私は一つの“新しい経営の型”を見た。
チームという家庭的共同体の力
大德さんの話には、常に「人」がいる。
スタッフ、クライアント、そして家族。
そのすべてが、彼女にとって“整える対象”であり、“支え合う構造”でもある。
夫の協力のもと、二人の子どもを育てながら会社を率いる彼女の姿は、
「家庭と仕事の両立」ではなく、 「家庭を含めた経営」という広がり を感じさせる。
彼女のチームには、共感を軸にした信頼関係がある。
それは競争よりも共鳴で動く組織だ。
整理整頓は単なる業務ではなく、「お互いを思いやる文化」であり、
企業文化の鏡として、働く人々の意識を映し出している。

設計的思考が生むバイタリティ
彼女の原動力は “ 片付け ” のではなく、“ 設計 ” だ。
複雑に絡み合った状況を一つずつ整理し、構造として再構成する。
だからこそ、彼女は「荒れた場所」「乱れた組織」「混沌とした現場」にこそ燃える。
人の“雑さ”を見た瞬間に、そこに潜む構造的な歪みを発見し、
「ここを整えれば人が変わる」と直感する。
それが彼女の言う「やる気のトリガー」であり、
仕事のバイタリティの源泉になっているのだ。
つまり、大德さんの整える力は“掃除の技術”ではなく、
“構造の設計力”そのものである。
教育としての片付け
話の最後に、彼女はこう語った。
「片付けは教育だと思っていて。子どもの頃から習慣化できるかで、大人になったときの“築ける力”が違う。」
彼女にとって「整える」とは、思考・行動・人間関係の三位一体をつくる行為である。
だから、オフィス改革と同じように、家庭や教育の現場にもこの思想を広げたいと話す。
単にきれいにするのではなく、
“自分の外側の世界に責任を持つこと”を育てる教育。
それは、今の個人主義が進む社会への静かなアンチテーゼでもある。

“美しさ”とは構造である
銀座という象徴的な地にオフィスを構え、テレビにも登場する。
外から見れば華やかだが、その裏側は緻密な設計と積み上げの結果である。
彼女の言う“美しさ”とは、外見のことではない。
「一つひとつの行為に、意味と構造があること」それが本当の美だと語る。
この思想は、ストラートデザインの理念そのものでもあり、
“見せるため”ではなく“続くため”の美しさを社会に根づかせている。
終章:整えることは、信頼をデザインすること
対談を終えて改めて感じたのは、
大德弘恵という人は、「整える」ことを通して、社会の信頼構造を再設計しているということだ。
変化を恐れず、自分の形を変えながらも軸を失わない
その在り方こそが、現代における“女性経営者の指標”だと感じた。
組織を整える。
人の意識を整える。
社会を整える。
彼女の仕事は、片付けではなく「文化のデザイン」である。 単なるオフィス改善ではなく、
“整えることを通して人が成長する社会”だ。
その思想は、今の日本企業が失いかけている「人間の輪郭」を取り戻す光になるだろう。
そしてその光の中心には、いつも大德弘恵という構造を設計する女性の姿がある。
大德弘恵さんを更にご紹介

【Beauty Japan 2025 東京大会】
総合グランプリ&Career賞グランプリ(詳細)
◆BEAUTY JAPANとは
→心・使命・生き方の美しさを評価する新時代のコンテスト(詳細)
◆実績
東京エリア大会
総合グランプリ受賞
キャリア部門グランプリ受賞
◆今後
日本大会グランドファイナリストとして活動中
2025年11月20日
横浜BUNTAIにて日本大会出場予定