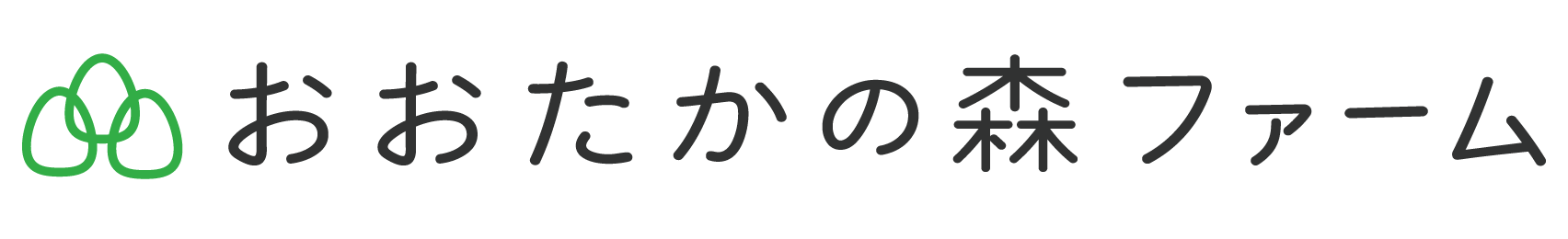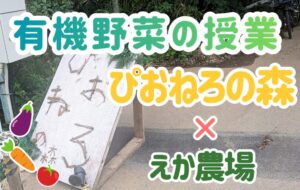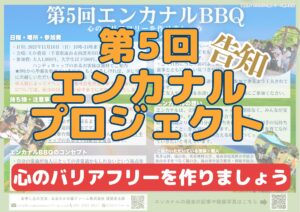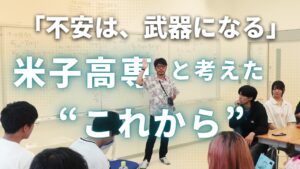千葉県印西市にあるフリースクール「ぴおねろの森」(HP)を訪れたとき、私はそこで理事を務める中村龍太さんに出会った。

サイボウズの執行役員であり、エンジニアであり、農業に携わる複業家でもある彼は、自らを「空気のような存在」と表現する。
「僕は子どもと一緒に何かをやるわけじゃないんです。名前を全部覚えて兄貴みたいに接するわけでもない。ただ子どもたちがどう動いているのかを抽象的に観察し、その自由さが本物なのかを実験している。フリースクールは、その実験を繰り返す場なんですよ」
彼の言葉からは、従来の「教育」や「指導」とはまったく異なる哲学が滲む。
教育は「教える側のエゴ」か
多くの教育活動は「子どものために何かをしたい」という大人の熱意から始まる。もちろんそれは大切な思いだ。しかし同時に、それはしばしば「教える側のエゴ」にもなりうる。
中村さんのスタンスは違う。彼は「子どもはたまたま子どもであるだけ」と捉え、特別視せずに「人が自由を感じられる環境とは何か」を考える。その設計力こそが、エンジニアとして培った感覚と深く結びついている。
実際、ぴおねろの森では子どもたちと一緒に「入室管理システム」を開発し、学校と出欠をリアルタイム共有する仕組みをつくり上げた。単に便利なIT導入にとどまらず、子ども自身がプロセスに関わることによって「自分たちが作った仕組み」という主体性が芽生えている。
「僕は “ 自由をどう設計するか ” に関心があるんです。子どもたちが “ 自由だ ” と実感できるかどうかは、与える側の思惑じゃなく、子どもがそう感じられるかどうかで決まる。その繊細な感覚を形にするのが僕の仕事なんです」


複業家という生き方
彼がこうした独自の教育観に至った背景には、サラリーマン時代の挫折がある。
NECから日本マイクロソフトへ転職し、新規事業で成果をあげながらマネジャーに昇進したが、部下の管理でつまずき、上司から「マネジャーは向いていない」と降格を告げられた。
「出世の道が閉ざされたと感じて、ものすごく苦しかった。でもキャリアコンサルタントから “ やりたいことは社外にあるんじゃないか ” と言われて、はっとしたんです」
その後サイボウズに転職し、週4日勤務+副業可という働き方を始める。農業や教育、起業を含め複数の仕事を同じ熱量で取り組むスタイルは、やがて「副業」ではなく「複業」と呼ぶようになった。
「収入の多さじゃなく、仕事から何を得られるか。人とのつながりや経験こそが自分を豊かにしてくれる。だから、すべての仕事を対等に扱っています」

信頼を設計する
視察中、私が強く感じたのは、彼が設計しているのは自由だけでなく「信頼」だということだ。
フリースクールは開設から5年を経て、地域から厚い信頼を獲得している。ボランティアが金銭ではなく「自分の表現の場」を求めて集まるのも、その信頼の証だ。
「人が持っている能力をどうすれば活かせるか。それを見極めて場を整えるのが僕の役割です。報酬のためではなく“ここで表現したい”と思える環境を作れたら、人は自然と力を発揮してくれる」
これはまさに彼が関心を持って執筆している「エフェクチュエーション」の実践だ。不確実な環境の中で、自分の手元の資源から始め、人との出会いを積み重ねながら未来を形にしていく。

子どもから地域へ
私自身、中村さんと話すなかで強く思ったのは、この発想を子どもだけでなく地域全体に広げられる可能性だ。老若男女を問わず、人がのびのびと表現できる空間を設計する。教育を「誰かが与えるもの」から「誰もが自由を感じる仕組み」へと拡張する。
地域全体が「学び合いの場」になれば、教育はもはや特定の世代に向けられるものではなく、人が生涯を通じて自由に育っていく営みとなる。
「僕は子どもに何かを直接伝えたいわけじゃない。大事なのは、彼らが自分で『自由だ』と感じること。その設計を、地域全体に広げていけたら面白いと思いますよ」
彼の穏やかな口調の中に、未来を切り開く確かな確信が宿っていた。

結び
教育の場において「教えること」はどうしても大人のエゴを帯びがちだ。だが中村龍太さんは、その枠を超えて「自由と信頼を設計する」という新しい形を示している。その姿勢はフリースクールを唯一無二の存在にし、そして今後は地域全体へと広がっていくだろう。
彼の実践は、「学び」とは何か、「自由」とは何かを私たち自身に問い直す。印西の森から始まった小さな実験は、社会にとって大きな示唆を持っている。